 疑問な人
疑問な人静かなときほど「キーン」「ジー」と耳鳴りが大きくなる…。病院で「異常なし」と言われたけれど、この音と一生つき合うの?
そんな不安を、本記事で体系的に整理していきます。



こんにちは、治療家まっちです!
耳鳴り(tinnitus)は耳そのものだけでなく、自律神経・血流・頸肩の筋緊張・睡眠・心理ストレスなど全身要因の影響を強く受けます。
加齢や騒音だけでなく、長時間のPC作業、首こり・顎関節のこわばり、寝不足、塩分やカフェイン、そしてメンタル負荷が絡み合い「鳴りやすい体内環境」を作ります。
重要なのは、音そのものをゼロにするだけを目標にせず、強度・頻度・気になり方(反応)を下げ、生活の占有度を落とすこと。
ここに鍼灸あん摩マッサージといった東洋医学的な施術や整体施術の強みが活きます。
そして耳鳴りは珍しい症状ではありません。
そこで、西洋医学の考えと東洋医学(中医学)の弁証を併走させ、鍼灸・整体・あん摩マッサージ指圧で根本から整える道筋を、セルフケアも含めて具体的にご案内します。
要点:耳鳴りは「耳だけの病気」ではなく、全身の巡りと神経系のバランスを映すサイン。だからこそ、全身を整える統合アプローチが効きます。
耳鳴りを根本から改善|茨城県古河市の鍼灸・整体院【あはき整体-治療院】
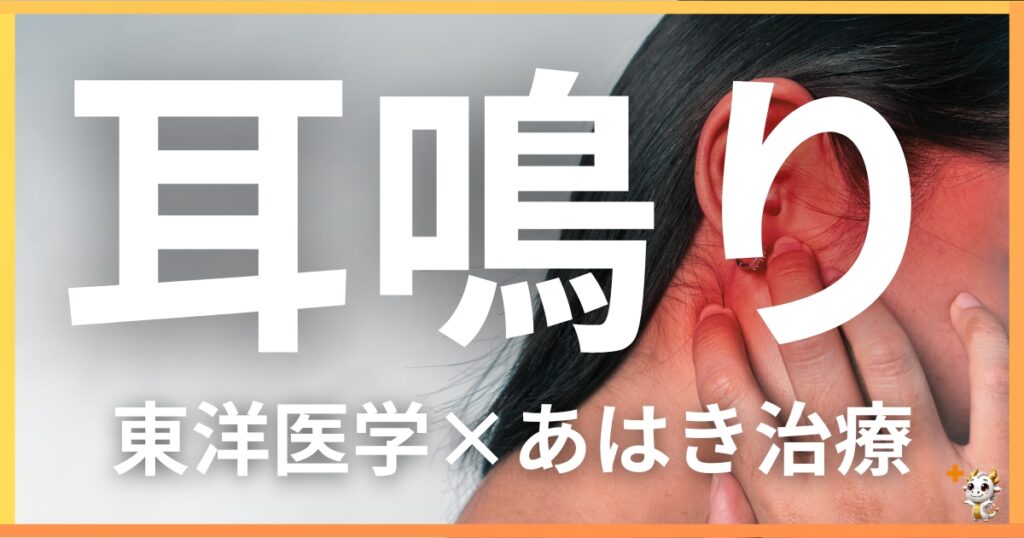
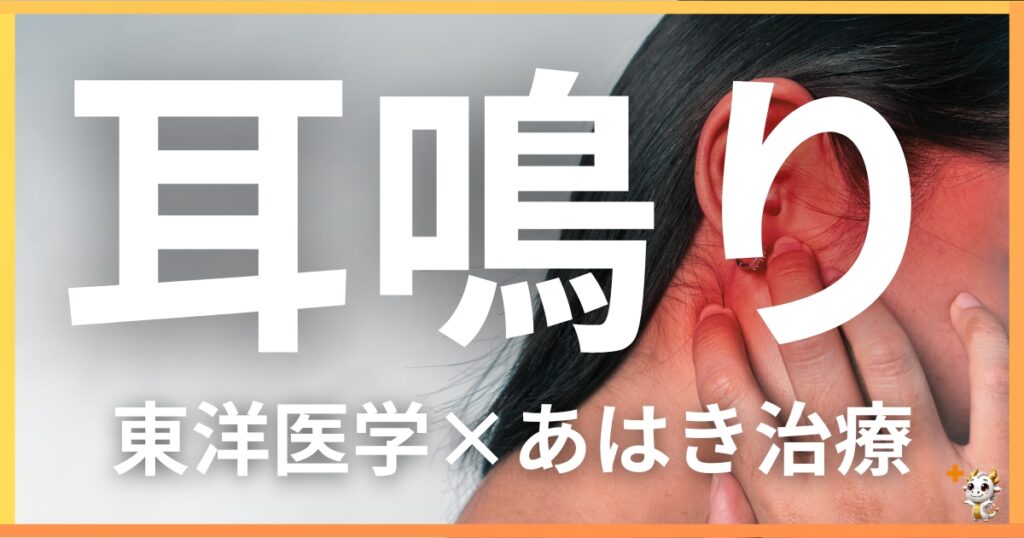
耳鳴りは、外の音がないのに「キーン」「ジー」「ゴー」と音を感じる状態の総称です。
音色(高音・低音)、連続/断続、片側/両側、発作性/持続性など表現は多彩で、難聴や耳閉感、頭重、肩こり、睡眠障害、不安が並走することも少なくありません。
まず押さえたいのは、①危険所見の除外(片側性・拍動性・神経症状の併発など)と、②日常の不快度(QOL)をどう下げるか、という二本柱です。
生理学的には、内耳の有毛細胞の変化、聴覚路の可塑性(過敏化)、頸部や顎関節などの体性(ソマト)性入力、自律神経の乱れ、血行動態の変化などが複合して「脳が音として解釈する」ことが核心です。
つまり治療の焦点は、音源(耳)だけでなく中枢の反応や体性要因にも広がります。



「どんな鳴り方で、どんな時に強まるか」を整理すると、改善の糸口が見えてきます!
西洋医学と東洋医学で耳鳴りを整理する


西洋医学と東洋医学、強みの違う二つの見方を重ねるほど、施術設計とセルフケアの精度が上がります。
まずはシンプルに要点を握りましょう。
西洋医学的なポイント
- 内耳・聴神経:加齢性/騒音性難聴、耳垢、炎症(中耳炎)など。
- 体性(ソマト)性:頸部筋・顎関節由来の入力で音の強弱が変わりうる。
- 血行動態:高血圧・動脈硬化・拍動性(血管性は要鑑別)。
- 中枢/心理:ストレス、睡眠障害、不安。認知行動療法や音響療法が活用される。
- 受診の目安:片側性、拍動性、急性の聴力低下、神経症状の併発は耳鼻科で評価。
東洋医学(中医学)的なポイント
- 腎虚:加齢・慢性疲労で腎精不足。高音性・夜間悪化。
- 肝火上炎:ストレスで気が上逆。発作的悪化、側頭部の張り。
- 痰湿:水湿の停滞。こもった低音、天候や食事で増悪。
- 血瘀:うっ血。頭重・肩こり、冷えの併発。
中医学は、耳(竅)と腎・肝・脾の関係、経絡の巡り(気血水)を整えることで、「鳴りやすい状態」そのものを下げていくのが特徴です。
局所+全身、当座の緩和+根本の体質改善という二層構えで進めます。



ガイドライン的思考(危険所見除外&QOL重視)+弁証論治(全身調整)のハイブリッドが、再現性の高い王道治療だね!
耳鳴りのタイプ別アプローチ
問診・視診・触診でタイプを仮決めし、セルフケア+専門施術を組み合わせます。
よく見られる4タイプを実践目線でまとめました。
① 高音「キーン」型(腎虚・慢性疲労ベース)
所見:夜間や静寂で増悪。睡眠の質が低い、冷えやすい。
施術:腎兪・太渓・三陰交で補腎益精。百会で全体調整。頸肩の緊張緩和。
セルフ:足湯、就寝前の3-5-8呼吸、就寝1〜2時間前の入浴、カフェイン控えめ。
② 低音「ゴー」型(血瘀・循環不良)
所見:頭重・肩こり、同一姿勢で悪化。冷えると増悪。
施術:膈兪・風池・合谷・百会。肩甲帯〜頸椎モビライゼーションで体性入力を鎮める。
セルフ:45〜60分ごとに立ち上がり、胸を開くストレッチ、こめかみ温罨法。
③ 「ジー」こもり型(痰湿・代謝低下)
所見:天候や湿度、甘い/冷たい飲食で悪化。耳閉感。
施術:陰陵泉・豊隆・中脘・三陰交で健脾化湿。
セルフ:温かい飲食、夕食は就寝3時間前まで、有酸素運動20〜30分。
④ 発作的悪化(肝火上炎・ストレス誘発)
所見:イライラ、眼精疲労、側頭部の張りで増悪。
施術:太衝・行間・風池・期門で疏肝理気。胸郭拡張と頸部筋膜の滑走を回復。
セルフ:画面オフのナイトルーティン、照明は暖色、夕方以降のカフェイン断ち。
受診の目安:片側性の急変、拍動性(ドクドク同期)、急性の聴力低下、神経症状の併発、発熱や耳痛を伴う場合は耳鼻科での評価を優先しましょう。
鍼灸・整体の有効性|どこに効くのか
耳鳴りは多因子性です。
万人に同じ手法が効くわけではない反面、症状強度・頻度・反応の仕方(つらさ)・睡眠の質をターゲットにすると改善が実感しやすく、研究でも一定の有用性が示されています。
要点は以下です。
- 鍼灸:耳周囲(耳門・聴宮・聴会など)+全身(腎・肝・脾の弁証穴)で自律神経を整え、過敏化した聴覚中枢の反応を穏やかに。頭皮鍼や電気鍼を症状に合わせて選択。
- 整体・手技:頸椎・肩甲帯・顎関節・舌骨周囲の筋膜を緩め、体性入力(Somatic)のノイズを低減。可動域の回復は血流・リンパ流改善にも寄与。
- 音環境・心理教育:完全無音を避ける、耳鳴り日誌で誘因を把握、認知行動療法的リフレーミングで「反応の仕方」を変える。
- 睡眠設計:就寝リズム、光・温度・呼吸。寝入りと寝起きの「儀式化」で自律神経の振れ幅を安定化。
当院では、初回で「何を優先的に下げるか(強度?頻度?就寝前のつらさ?)」を共有し、2〜4週のトライアルで反応を見て施術計画を最適化します。
今日からできるセルフケア5選
「完璧にやる」より「軽く毎日」がポイント。耳鳴りの閾値を少しずつ下げていきましょう。
- 呼吸:3秒吸って5秒止めて8秒吐く×5分。朝、就寝前に。吐く時間を長く。
- ツボ押し:風池(うなじ)・聴宮(耳前)・太衝(足の甲)を10〜15秒×数回やさしく。
- 温熱:耳周囲〜後頭部に蒸しタオル1〜2分。頸を冷やさない。
- 姿勢:45〜60分ごとに立ち、胸を開いて深呼吸。顎は軽く引く。
- 生活:カフェインと塩分は控えめ、就寝2時間前はデジタルの画面オフ、BGMは小さく穏やかに。



セルフケアは「気にしにくい時間帯を増やす」ことが目的。小さな成功を積み上げましょう!
十二経脈病証からみた「耳鳴り」の治療法(主穴・随証・所見・方針・セルフ)
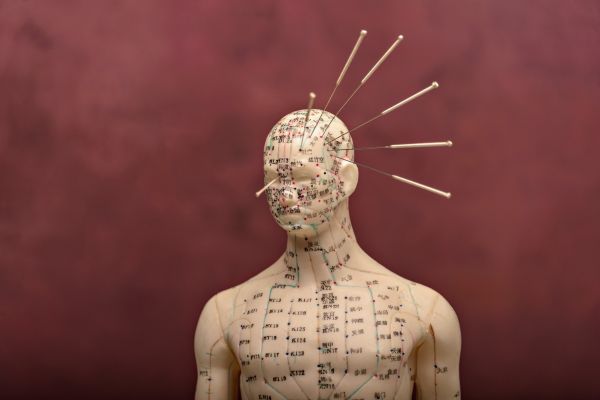
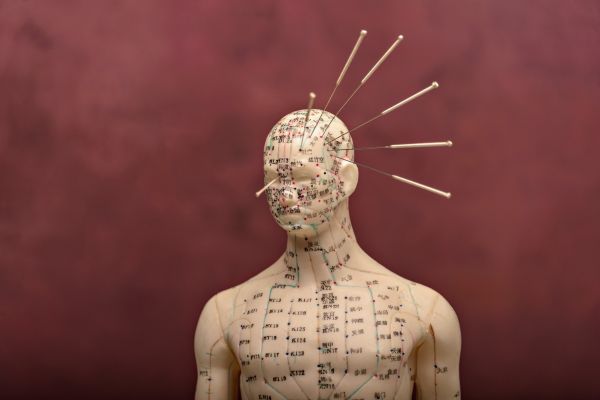
耳鳴りは性質(高音/低音)・誘因(ストレス/疲労/冷え/気圧/食後)・随伴(耳閉/めまい/肩こり/睡眠障害)から経脈を絞り、主穴+随証穴+体性連動(頚肩・顎・側頭)で設計します。以下は臨床テンプレです(症状に応じ取捨選択)。
1)足少陰腎経(慢性・高音・夜間悪化)
所見:高音の「キーン」、夜間や静寂で強まる、冷えや疲労で悪化、腰膝だるさ・乾燥・寝汗を伴いやすい。
方針:補腎益精・安神。深部の温かさと睡眠の質を底上げして過敏性を鎮める。
主穴:腎兪・太渓・三陰交。
随証:命門(温補)/百会(自律安定)。
セルフ:腹腰保温(腹巻/湯たんぽ)・就寝90分前の微温浴40℃×10–15分→腹式呼吸3分・夜カフェイン/画面光を控える。
2)足厥陰肝経(ストレス誘発・発作性)
所見:イライラや緊張後に発作的に増悪、側頭部〜こめかみの張り、眼精疲労・光音過敏を伴うことが多い。
方針:疏肝理気・清肝。側頭部の筋膜緊張と自律の高ぶりを解く。
主穴:太衝・行間・風池。
随証:期門(胸脇の解鬱)/合谷(上焦の疏通)。
セルフ:「4–6呼吸」2〜3分×2/日・側頭筋/咬筋のやさしいリリース・20-20-20(画面20分ごとに20秒遠方を見る)。
3)足太陰脾経(痰湿・こもった低音)
所見:低音の「ゴー/ボー」、耳閉感、食後だるさ・むくみ・頭重、苔厚膩。
方針:健脾化湿。体液代謝と中焦の巡りを整え耳管の通りを改善。
主穴:陰陵泉・豊隆・中脘。
随証:三陰交(体液調整)。
セルフ:白湯を少量頻回・甘味/脂質/冷飲の連続を控える・食後10〜15分の軽歩・鼻呼吸を意識。
4)督脈・足太陽膀胱経(血瘀・頚肩こり)
所見:頚肩の強いこり・頭重、顎関節のこわばり、寒冷/姿勢で変動、側頭〜耳周囲の筋緊張。
方針:活血化瘀+体性連動調整。頚肩・顎・側頭の滑走を回復し血行とリンパを促す。
主穴:百会・膈兪・肩外兪・委中。
随証:耳門・完骨(局所循環)。
セルフ:30〜45分毎に姿勢リセット(首すくめ→脱力)・肩甲骨寄せ10回・咀嚼筋のやさしいストレッチ・就寝前のホットタオルを後頚部へ。
ワンポイント:百会・風池・太衝は多タイプで応用可。局所(耳前後)+遠位(手足)+連動(頚肩/顎)の“三点セット”を意識すると再現性が上がります。
ツボ選択の流れ(実践テンプレ)
- ① 症状像を分類:高音/低音、片/両側、発作/持続、増悪因子(ストレス・冷え・気圧・食後・姿勢)。
- ② 経脈を仮決め:腎経/肝経/脾経/膀胱経+督脈(必要に応じて三焦・胆の耳周囲連絡も考慮)。
- ③ 主穴2〜3+随証1〜2:局所+遠位+連動で三層構成。
- ④ 技法:慢性は温灸・置鍼、急性増悪は軽刺激で鎮静。
- ⑤ 生活設計:睡眠(就寝前ルーティン)・音環境(静けさを作り過ぎない)・カフェイン/アルコール調整・画面時間を最適化。



「どの経脈を狙うか」が決まれば、施術はシンプルに、効果はクリアに出ます。
茨城県古河市での耳鳴り施術|あはき整体-治療院


当院(茨城県古河市の治療院・鍼灸院・整体院)では、耳鳴りに対し以下を軸にオーダーメイドで対応します。
- 評価:鳴り方・誘因・時間帯・頸肩/顎の所見・睡眠・食事・ストレスを丁寧に聴取。
- 鍼灸:耳周囲+全身(腎・肝・脾)を整える。必要に応じ温灸/頭皮鍼も。
- 整体・手技:頸椎の配列、肩甲帯、舌骨・顎関節の連動改善で体性要因を低減。
- セルフ設計:呼吸・姿勢・音環境・就眠儀式を一緒に作り、再発しにくい日常へ。
「強度を下げ、気にしない時間帯を増やし、睡眠を守る」——この順序で、2〜4週の変化を一緒に確認しながら前に進みます。
古河市近郊で耳鳴りの鍼灸・整体をお探しの方は、お気軽にご相談ください。
\ 24時間受付・ご相談だけでもOK /



まずは現状整理から。最短ルートを一緒に組み立てましょう!
関連:めまい・BPPV・PPPDとの関係
耳鳴りはめまい(良性発作性頭位めまい症:BPPV、持続性知覚性姿勢誘発めまい:PPPDなど)と併発することがあります。
共通因子は、姿勢・自律神経・頸部筋の緊張。
耳だけにフォーカスせず、全身の連動性を整えることで、「揺れやすさ」と「鳴りやすさ」が同時に下がるケースは少なくありません。
併発が疑われる場合も、評価と施術をワンストップで設計します。
注意:急な激しいめまいと片側の耳鳴り・難聴、神経症状(ろれつ、脱力など)を伴う場合は、救急・耳鼻科での評価を優先してください。
さいごに|耳鳴りは「変えられる体験」へ


耳鳴りは、音そのものを完全に消すことだけに囚われると行き詰まりやすい症状です。
しかし、強度・頻度・気になり方、そして眠りや集中を守るという観点で一歩ずつ整えれば、確かな変化を積み上げられます。
ガイドラインの思考と東洋医学の全身調整を橋渡ししながら、あなたの体に合う最適解を一緒に探しましょう。
「夜になると音が強い」「肩とこめかみが張ると増す」「検査は異常なし。でも困っている」——ひとつでも当てはまるなら、いつでもご相談ください。
茨城県古河市の地域密着の治療院・鍼灸院・整体院として、やさしく、確実に前進するための伴走をお約束します。



一人で抱え込まないで。今日からできることを、一緒に始めましょう!


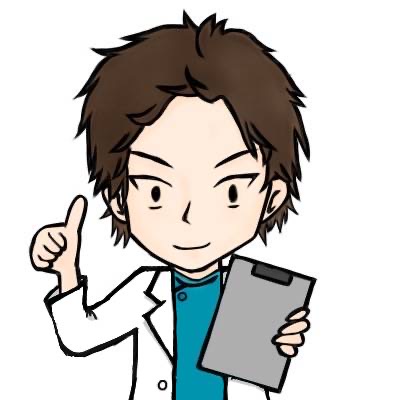



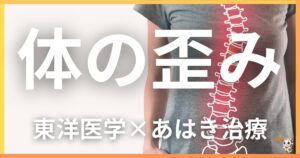

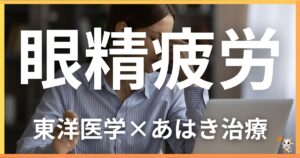





コメント