 疑問な人
疑問な人夜泣き・黄昏泣き・かんしゃく・食べムラ…「疳(かん)の虫」って結局なに?どうすれば落ち着くの?
こんな悩みを解消します。



こんにちは、治療家まっちです!
本記事では、昔から言われる「疳の虫」を、西洋医学(乳児期コリック/睡眠・消化・感覚の問題)と東洋医学(中医学の弁証/経絡)の両面から整理。ご家庭で今日から実践できる工夫と、鍼灸・整体・小児はりで何ができるかを具体的に解説します。
「疳の虫」は医学用語ではありませんが、乳幼児の“泣き/不機嫌/過覚醒/食のムラ/便通のゆらぎ”をまとめて指す生活語として広く使われます。西洋医学では、月齢や様式に応じて乳児期コリック(Infantile Colic)、睡眠/自律の未成熟、機能性消化管症状などとして評価します。ローマ基準(Rome IV)は、5か月未満・明らかな原因なく反復/持続する泣き・不機嫌・発熱や体重不良など病的所見がないことを診断の骨子としています。
まずは安全ライン(レッドフラッグ):38℃以上の発熱(特に3か月未満)/顔色不良/活気低下/哺乳不良/胆汁様嘔吐・血便/発疹+発熱/呼吸が苦しそう/けいれん/強い持続痛/脱水(尿が少ない・涙が出ない・口が渇く・泉門陥凹)…これらは速やかに小児科へ。迷ったら受診が原則です。
「疳の虫」を根本から整える|茨城県古河市の鍼灸・整体院【あはき整体-治療院】
5つの柱:①危険サインの共有(安心して様子を見られる土台づくり)②生活リズム(睡眠・抱き方・環境刺激)③消化(授乳/ミルク/げっぷ/便通)④必要に応じた医療的管理(アレルギー/GER/便秘など)⑤小児はり/鍼灸×整体で自律と巡りをやさしく調整。
用語メモ:乳児期コリックは2〜6週頃に増え、6週でピーク、3〜4か月で軽快〜6か月で消失が一般的。親御さんの負担が大きく、評価と説明、安心できるプランが重要です。
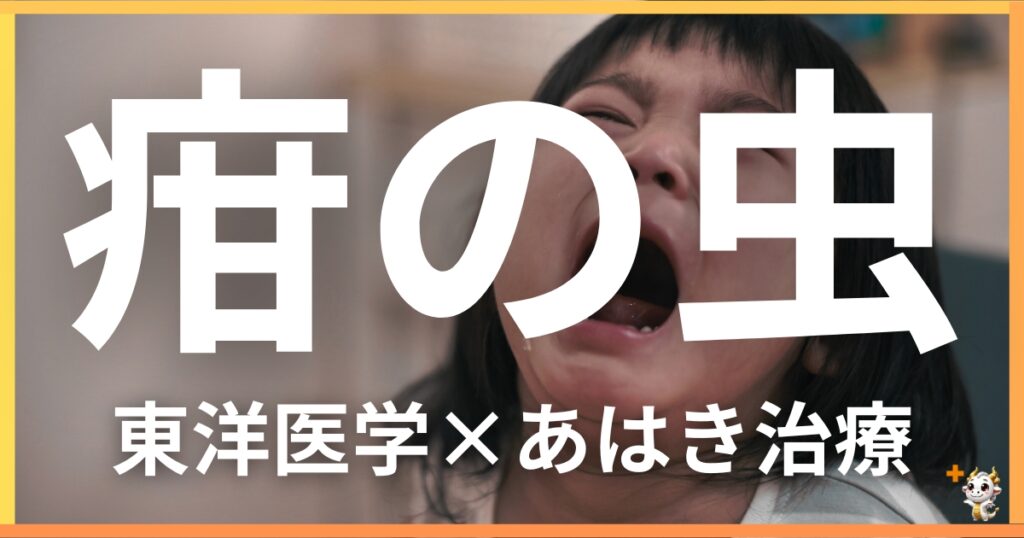
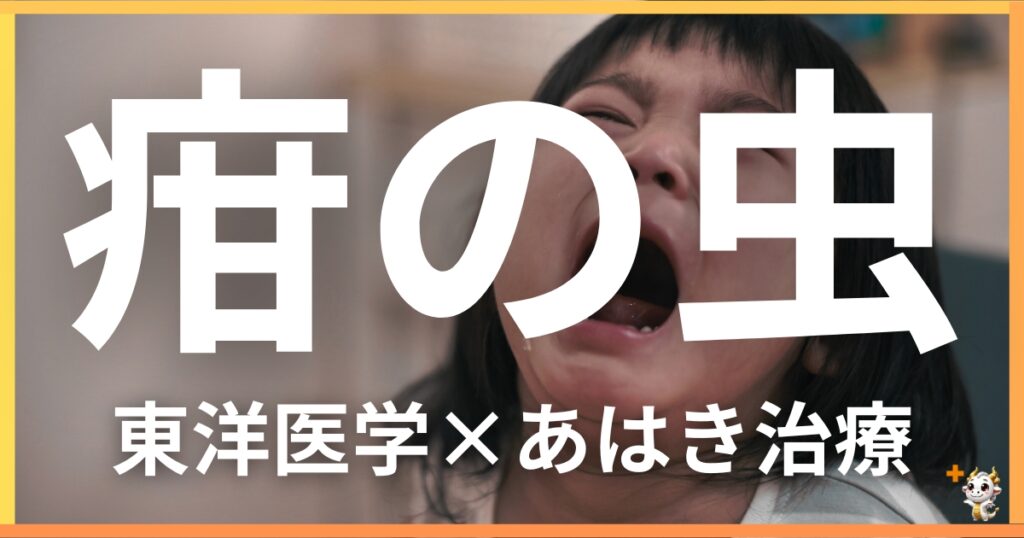
西洋医学と東洋医学からみた「疳の虫」
西洋医学の整理(乳児期コリック/自律の未成熟)
- 定義:Rome IV:5か月未満で、明らかな原因なく反復/持続する泣き・不機嫌。発熱/体重不良などは伴わない。
- 鑑別:耳炎・尿路感染・ヘルニア嵌頓・GERD・ミルク蛋白アレルギー・髄膜炎など。評価は臨床診断が基本で、危険サインがなければ経過で軽快。
- 経過:2〜3週発症、6週ピーク、3〜4か月で改善が大多数。
- 対応:抱き方/ゲップ/環境刺激を整え、親教育とストレスケアを重視。必要に応じて消化・授乳の見直し。
補助療法・栄養介入のエビデンス
- プロバイオティクス:Lactobacillus reuteri DSM 17938は母乳栄養児で泣き時間短縮のエビデンスが比較的強い報告。式乳児や帝王切開児では結論が限定的。
- 鍼(乳児コリック):系統的レビューでは有望とする報告と、一般推奨までは至らないとする報告が混在。安全性は訓練を受けた施術者の下で概ね良好とされるが、侵襲は最小限に。
- 親支援:過度な泣きは保護者の疲弊/PND(産後うつ)や児の虐待リスクと関連するため、ケア者支援が治療の一部。
東洋医学(中医学)の見立て
- 軸:脾胃の未熟(胃気上逆/脾虚)+肝(疏泄:情緒/筋の緊張)+腎(成長の土台)、時に痰湿/風熱のからみ。
- 狙い:小児はり/接触鍼(刺さない鍼)・軽刺激の鍼灸で胃気を下し、肝の過敏を鎮め、睡眠-消化-情動の循環を整える。
当院では、日本伝統の小児はり(刺さないスプーン様の器具等)を中心に、ご家庭で続けられる撫でさすり/ツボ押しもお渡しします(安全第一・刺激は最小)。小児はりは非侵襲で受け入れやすく、親子ともに落ち着きやすいのが特徴です。
症状タイプ別の特徴とアプローチ
① 乳児期コリック(0〜5か月)
所見:夕方〜夜にかけて泣きが強い/反り返る/ガス・腹部膨満、体重は保たれる。
家庭:抱き方のバリエーション(前抱き/コアラ抱き)、ゲップ・授乳/哺乳の姿勢、環境刺激の調整(光・音・匂い)を整える。
補助:母乳児でL. reuteri DSM17938が有望(医師と相談)。
施術:内関・中脘・足三里の軽刺激+腹部のやさしいマッサージ。
② 睡眠/過覚醒優位型(夜泣き・まとまらない睡眠)
所見:入眠に時間/刺激に敏感/日中の睡眠リズムがばらつく。
家庭:同じ順番での入眠ルーティン・光量/温度/騒音の整理。抱っこ〜置く時は段階的に。
施術:百会・神門・内関・三陰交の軽刺激、小児はりで背〜耳周囲をスイープ。
③ 消化器優位型(ガス・便秘/軟便・ミルク不耐)
所見:腹部膨満・ガス/便通のゆらぎ・げっぷ困難。
家庭:授乳姿勢・げっぷ・腹部ののの字マッサージ・温罨法。必要に応じ配合ミルクの相談や蛋白アレルギー疑いは医師へ。
施術:天枢・中脘・足三里・陰陵泉の軽刺激。
補助:プロバイオティクスはケースバイケース(母乳児で有望)。
④ 感覚過敏・環境トリガー型
所見:明るさ/音/匂い/人混みで増悪、抱き方/衣類の縫い目なども影響。
家庭:刺激を“足す/引く”を試し、静かな場所と短い外気浴をリズム化。
施術:太衝・合谷・百会・風池の軽刺激+胸郭のやわらげ。
⑤ 幼児期移行(かんしゃく・食べムラ・眠りの浅さ)
所見:夕方の不機嫌/ルーティン変更で悪化/便通が不安定。
家庭:予告と選択肢で見通しをつくる、夕方の補食/水分を工夫。
施術:脾胃を立て直す(中脘・足三里)+肝の疏泄(太衝)+睡眠の安定(神門・内関)。
受診の目安:泣き方が急に変わる、持続的な嘔吐や胆汁様嘔吐、血便、強い発疹+発熱、尿が極端に少ない/ぐったり——まず小児科へ。
鍼灸・小児はり・整体の有効性と研究報告
- 乳児コリック×鍼:RCT/レビューで「泣き時間短縮の可能性」報告と「一般推奨は時期尚早」の両見解。家族と相談し最小刺激・短時間・有資格者での実施が前提。
- 安全性:小児鍼の有害事象は主に軽微(痛み/出血/皮下出血)で、重篤例は稀。ただし胸部/深部への刺鍼は避け、小児専門の訓練と衛生管理が必須。
- プロバイオティクス:L. reuteri DSM17938は母乳児で泣き時間短縮のメタ解析。配合/用量/期間は医療者と確認。
- 親教育:泣きのピークや自然経過の説明・ケア者休息の確保が介入の中核。
※当院の小児ケアは小児はり(刺さない接触刺激)を基本とし、必要時に極細鍼を最小本数で使用。月齢/体格/既往/家族の同意を必ず確認します。
セルフケアと生活習慣(親御さん保存版)
- 抱き方・姿勢:前抱き/コアラ抱き/横向き抱きでゆっくり角度変更。げっぷは背中を丸めすぎず“胸郭に余裕”。
- ルーティン:入眠前の流れ(暗く/静かに/同じ順番)。昼間の散歩で体内時計を整える。
- 環境:光と音を弱め、衣類のタグ・縫い目・温度差を最小化。
- 消化:授乳姿勢の調整、腹部ののの字マッサージ、温罨法。母乳児でプロバイオティクスは主治医に相談。
- 親の休息:交代制/20分の仮眠/家事の外注。泣きが続く時は安全な寝床に置き、深呼吸と水分補給(危険サインがなければ“離れる勇気”もケア)。



来院時は、ご家庭の“続けられる分量”に合わせてスケジュール化します!
十二経脈病証からみた「疳の虫」の治療法


小児の「疳の虫」は、脾胃(消化/運化)と肝(疏泄/情動)のアンバランスに、三焦(体液/環境適応)や心包(自律)が絡みやすいのが特徴です。以下は所見→主穴→随証→セルフで具体化した実装テンプレです(小児は軽刺激/接触刺激が原則)。
1)足太陰脾経(消化未熟・食後不機嫌・便通のゆらぎ)
所見:食後のぐずり、腹部膨満、便秘と軟便の交替、舌苔白〜やや厚。
主穴:中脘・足三里・陰陵泉。
随証:天枢(蠕動)/公孫(衝任調整)。
セルフ:授乳/哺乳の姿勢最適化、げっぷ、腹部「の」の字マッサージ、ぬるめの温罨法。
2)足陽明胃経(げっぷ困難・逆流・ガスが多い)
所見:吐乳/さかのぼり、ガスで反り返る、夜間増悪。
主穴:内庭・梁丘・足三里。
随証:中脘(胃気を下す)/内関(悪心)。
セルフ:哺乳角度を高めに、授乳後は上半身やや挙上、短時間の縦抱きで静置。
3)足厥陰肝経(かんしゃく・夕方悪化・反り返り)
所見:刺激で悪化、胸脇張り、顔紅、入眠困難。
主穴:太衝・行間・期門。
随証:百会(鎮静)/神門(情動)/合谷(上焦の巡り)。
セルフ:光/音/匂いを控えめにし、抱っこの角度変化をゆっくり行う。夕方は短い外気浴+水分。
4)手厥陰心包経(夜泣き・自律の高ぶり・不安)
所見:入眠に時間、すぐ目覚める、ドキッとしやすい。
主穴:内関・郄門・膻中。
随証:神門(安眠)/百会(自律)。
セルフ:毎晩同じ入眠ルーティン(暗く→静か→同じ順番)、胸郭なでさすり、小児はりの接触刺激。
5)手少陽三焦経(体液代謝・環境過敏・耳/鼻まわり)
所見:湿度/気圧・人混み・音で増悪、鼻づまり/耳周囲の違和感。
主穴:外関・中渚・耳門(SJ21)。
随証:風池(頭項の緊張)/合谷(上焦疏通)。
セルフ:室温/湿度の微調整、静かな環境で短時間の刺激曝露→休憩のサイクルづくり。
ワンポイント:小児は刺さない小児はり(接触刺激)やご家庭の撫でさすりで十分に反応します。刺激は“最小で十分”。症状が波打つ時間帯(夕方など)に合わせ、主穴2〜3+随証1〜2を短時間で。
ツボ選択の流れ(実践テンプレ)
- ① サイン把握:泣く時間帯(夕方/夜間)・誘因(刺激/空腹/便通/眠気)・随伴(吐乳/ガス/寝汗)。
- ② 経脈仮決め:脾・胃(消化)/肝(情動)/心包(自律)/三焦(環境適応)。
- ③ 取穴:主穴2〜3+随証1〜2(局所+遠位)。小児は接触/軽刺激が基本。
- ④ 施術時間:短時間(数分)でOK。夕方〜就寝前に集中実施。
- ⑤ 家庭ケア:抱き方/げっぷ/環境(光・音・温湿度)/腹部ケアを“続けられる分量”で回す。
経脈の滞りをほどきつつ、生活のリズムを整える——“最小刺激×続けやすさ”が合言葉です!家庭ケア(抱き方・環境・消化)を併走。
茨城県古河市での「疳の虫」ケア|あはき整体-治療院


- 小児はり:刺さない接触刺激で自律を穏やかに整える(背〜腹〜四肢を短時間スイープ)。
- 鍼灸(最小刺激):必要時に極細鍼を短時間、内関/中脘/足三里など。
- 整体:抱っこ・授乳・寝床の姿勢づくり、胸郭や腹部の“やわらげ”。
- 生活設計:入眠ルーティン/光・音/げっぷ/腹部ケア/親の休息動線を個別化。
- 医療連携:レッドフラッグはまず小児科へ。GERD/アレルギー/便秘の医療管理とも併走。
\24時間受付中/



“我慢”ではなく“仕組み化”。親子にやさしいプランで伴走します!
さいごに


「疳の虫」=親の頑張り不足ではありません。多くは時間とともに改善する発達上のゆらぎであり、危険サインの除外→生活の微調整→必要時の補助療法が王道です。
母乳児の一部にはL. reuteriが有効なこと、鍼灸/小児はりはエビデンスが混在しつつも、最小刺激・安全第一で“穏やかに整える”選択肢になりうることを丁寧にお伝えします。
当院は、鍼灸×小児はり×整体×生活設計を一本化し、ご家庭で継続できる分量に落とし込みます。
レッドフラッグはまず医療へ、それ以外の多くの“疳の虫”は、親子のリズムに寄り添う小さな工夫の積み重ねで確実に波が小さくなります。
茨城県古河市の治療院・鍼灸院・整体院として、安心して毎日を過ごせるよう、二人三脚で伴走します。

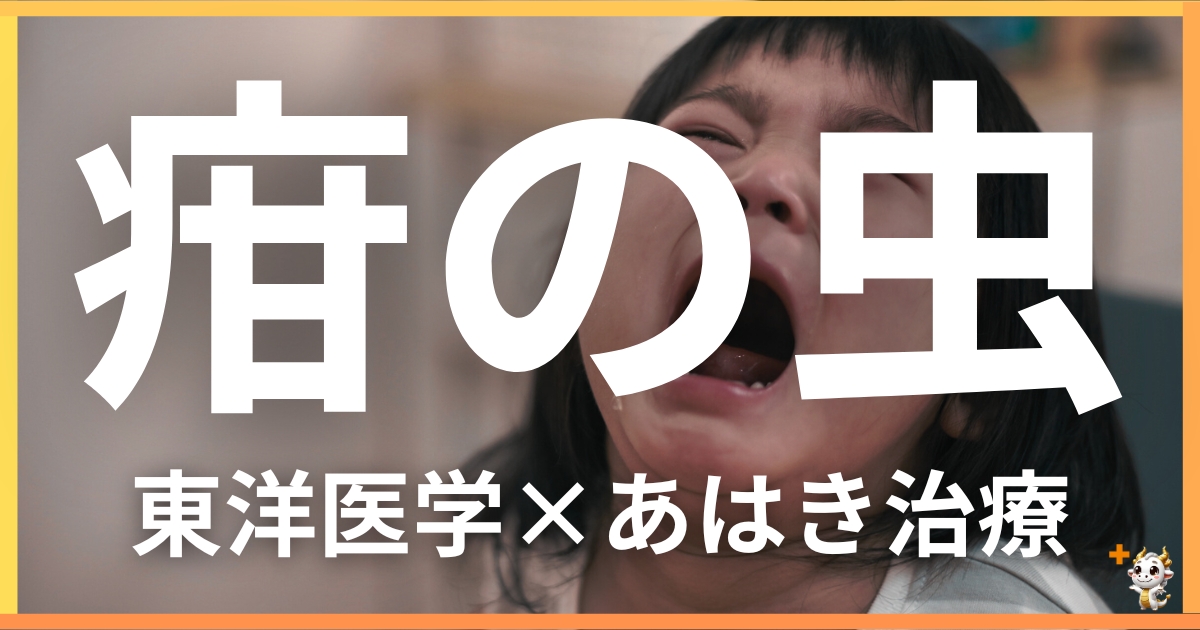
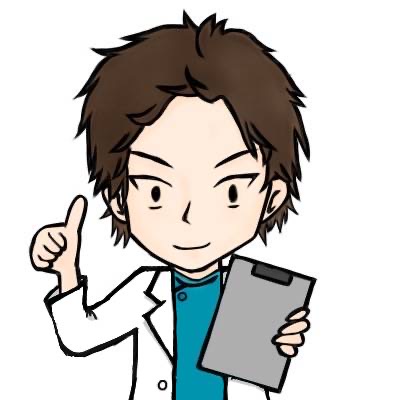



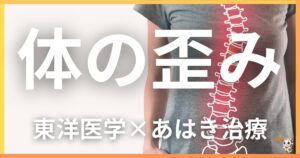

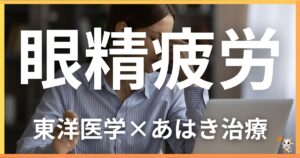





コメント